

本学園の教員インタビュー企画です。十人十色の生徒同様、個性あふれる教員が揃う正則学園。それぞれ形も色も違えど、己が胸に抱く決意、熱意はみな同じ。男子たるものという固定観念に捉われず、生徒一人ひとりの自主性を重んじ、その夢や希望を支える本学園の教員たちに、各々の熱き胸の内を語っていただきました。
-
 小嶋 校長
小嶋 校長
-
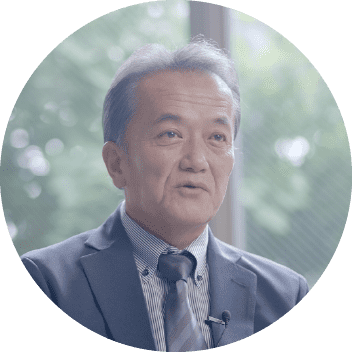 小林 理事長
小林 理事長
-
 臼井 先生
臼井 先生
-
 飯田 先生
飯田 先生

部活動について

部活動について
花いけ男子部、ビッグバンド部、蜜蜂倶楽部(SGBees!!)、フラッグフットボールという4つの部活の顧問をやっています。
花いけ男子部については、花いけは女性のイメージが強いと思いますし、私自身も花をいけた事が実は無くて、ただ花や植物が好きな気持ちは元々あったんです。そんななかで偶然、高校生花いけバトルの存在を知りました。ルールの中にも自由性があって自主性や想像力も育める。これはスポーツでもあり文化的でもあって面白い
花いけ男子部、ビッグバンド部、蜜蜂倶楽部(SGBees!!)、フラッグフットボールという4つの部活の顧問をやっています。
花いけ男子部については、花いけは女性のイメージが強いと思いますし、私自身も花をいけた事が実は無くて、ただ花や植物が好きな気持ちは元々あったんです。そんななかで偶然、高校生花いけバトルの存在を知りました。ルールの中にも自由性があって自主性や想像力も育める。

なぁという感想と、女性がいけるものというイメージを変えてみたいなという想いが生まれました。男の子はこうしなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないっていうのが僕の中には無くて、生徒たちの新しい発見になればなぁと。男の子ってどちらかといえば雑とかガサツとかってイメージが非常に強い。そういうところを踏まえて、実践を重ねて所作を学んでイメージを変えていきたいという思いから花いけ男子部を作りました。
花をいける人はかっこいい。
より輝きたいなと思っています。
これはスポーツでもあり文化的でもあって面白いなぁという感想と、女性がいけるものというイメージを変えてみたいなという想いが生まれました。男の子はこうしなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないっていうのが僕の中には無くて、生徒たちの新しい発見になればなぁと。男の子ってどちらかといえば雑とかガサツとかってイメージが非常に強い。そういうところを踏まえて、実践を重ねて所作を学んでイメージを変えていきたいという思いから花いけ男子部を作りました。
花をいける人はかっこいい。
より輝きたいなと思っています。

養蜂倶楽部については、養蜂をやろう!って言った時に生徒がどれくらい集まるかなと思ったんですけど、80人くらい集まって驚きました(笑)。ちょうどテレビの特集などで話題性があったかもしれませんが、採蜜、つまり蜂蜜を採取するという成果物があることが彼らの興味関心を引いたんだと思います。うちは養蜂の環境も良いですし、自然栽培と合わせて伸びやかに活動しています。
ビッグバンド部は、実は18年やっています。これまで多くのイベントに参加してきましたが、今自分たちが一番力を入れている活動は地元のイベントに出ることですね。大きなコンペティションなどもありますが、その結
養蜂倶楽部については、養蜂をやろう!って言った時に生徒がどれくらい集まるかなと思ったんですけど、80人くらい集まって驚きました(笑)。ちょうどテレビの特集などで話題性があったかもしれませんが、採蜜、つまり蜂蜜を採取するという成果物があることが彼らの興味関心を引いたんだと思います。うちは養蜂の環境も良いですし、自然栽培と合わせて伸びやかに活動しています。
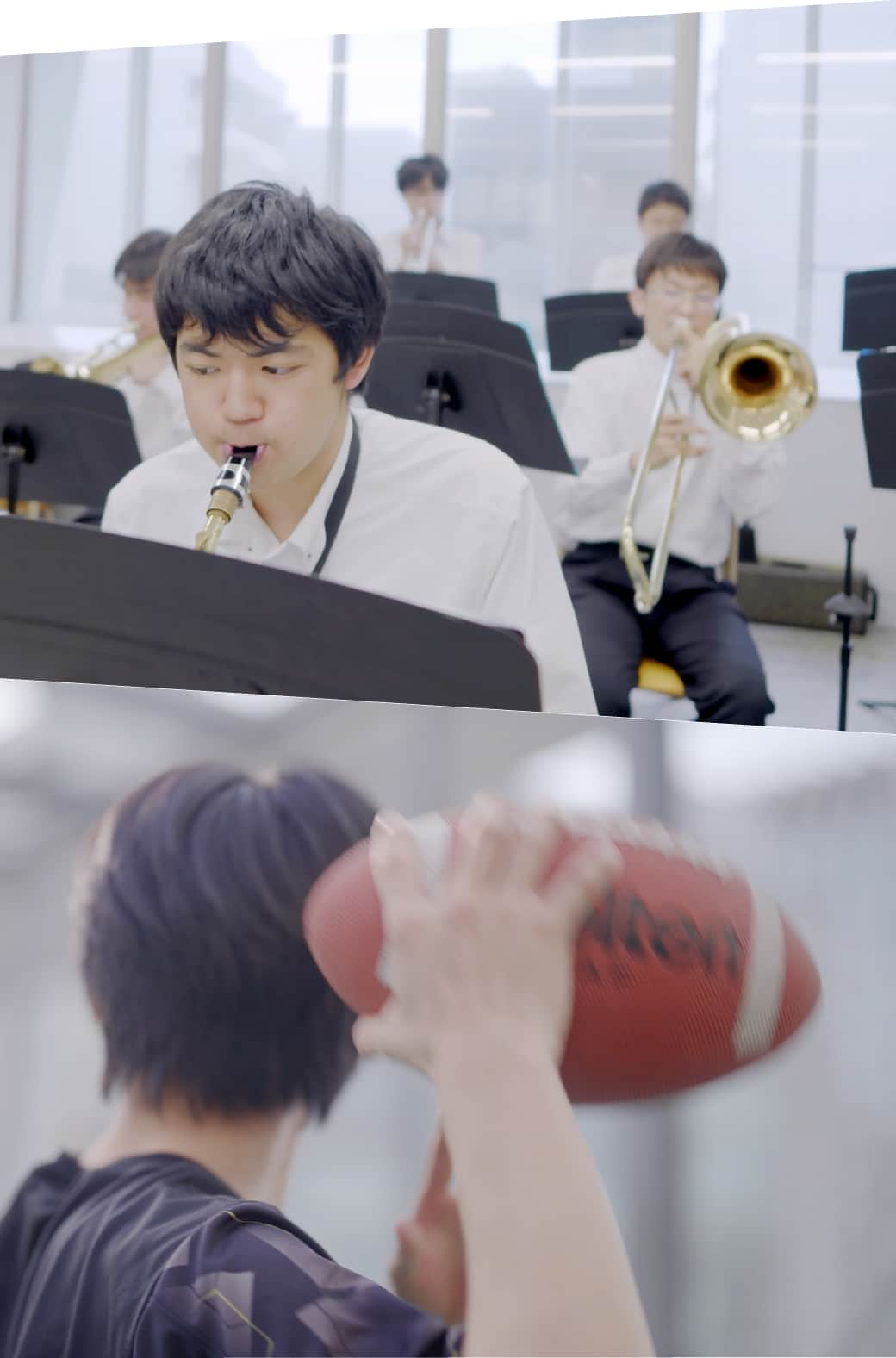

果に一喜一憂するのではなく、地元神田をはじめ広くは東京や関東近郊のイベントで、初めて私たちの演奏を聴く方々が立ち止まってくれるかどうか。それが私たちの勝負なんです。一曲でも聴いてくれるかどうか。演奏を聴いてくれた方が「君たち本当に高校生なの?」って驚いてくれることが私たちのご褒美ですね(笑)。成功体験といいますか、やってきて良かったなっていう達成感。失敗しても、ああすれば良かったこうすれば良かったという経験を勉強に活かすこと。そういう気持ちを部活動から学んでほしいですね。
フラッグフットボールは、アメリカンフットボールの小さい版と捉えてもらえると分かりやすいです。2028年のロサンゼルスオリンピックの正式種目にも決定し、安全性も高く小学校でも普及し始めています。私自身NFLが大好きで今でも試合は欠かさず観ていますが、自分でもなにか近いものが出来ないかと模索していたので、良い機会と思い切って部を創設しました(笑)。やったことない経験とか、やったことはあるけどそれを部活動でやってみようとか、他の部活と兼部しながらも3年間全うするってことは、彼らにとってとても大切な経験になると思いますし、うちの部活動の魅力の一つだと思います。
ビッグバンド部は、実は18年やっています。これまで多くのイベントに参加してきましたが、今自分たちが一番力を入れている活動は地元のイベントに出ることですね。大きなコンペティションなどもありますが、その結果に一喜一憂するのではなく、地元神田をはじめ広くは東京や関東近郊のイベントで、初めて私たちの演奏を聴く方々が立ち止まってくれるかどうか。それが私たちの勝負なんです。一曲でも聴いてくれるかどうか。演奏を聴いてくれた方が「君たち本当に高校生なの?」って驚いてくれることが私たちのご褒美ですね(笑)。成功体験といいますか、やってきて良かったなっていう達成感。失敗しても、ああすれば良かったこうすれば良かったという経験を勉強に活かすこと。そういう気持ちを部活動から学んでほしいですね。
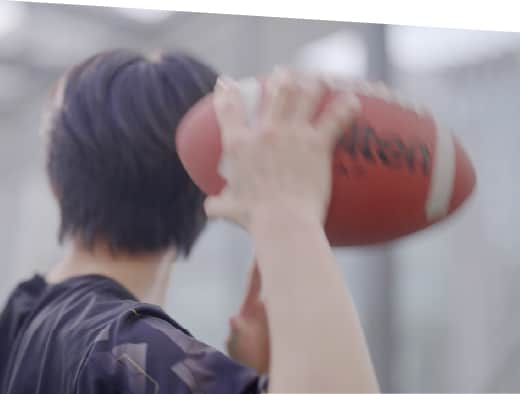
フラッグフットボールは、アメリカンフットボールの小さい版と捉えてもらえると分かりやすいです。2028年のロサンゼルスオリンピックの正式種目にも決定し、安全性も高く小学校でも普及し始めています。私自身NFLが大好きで今でも試合は欠かさず観ていますが、自分でもなにか近いものが出来ないかと模索していたので、良い機会と思い切って部を創設しました(笑)。やったことない経験とか、やったことはあるけどそれを部活動でやってみようとか、他の部活と兼部しながらも3年間全うするってことは、彼らにとってとても大切な経験になると思いますし、うちの部活動の魅力の一つだと思います。
高校教師を目指した理由

中学時代は教員を目指そうとは全く考えておらず、実家の家業を継ごうと思っていたのですが、「自分の将来は自分で決めなさい」という親の助言と、高校時代の恩師のご指導のおかげで、中学時代は好きでもなかった数学が次第に楽しくなって、教員になれたらいいなという思いが芽生え始めました。
私は中高の教員の免許を持っていますが、中学ではなく高校の教員を選んだ理由は、男と男として向き合いたいというのが本当に大きかったんです。男の子は思春期に
中学時代は教員を目指そうとは全く考えておらず、実家の家業を継ごうと思っていたのですが、「自分の将来は自分で決めなさい」という親の助言と、高校時代の恩師のご指導のおかげで、中学時代は好きでもなかった数学が次第に楽しくなって、教員になれたらいいなという思いが芽生え始めました。
私は中高の教員の免許を持っていますが、中学ではなく高校の教員を選んだ理由は、男と男として向き合いたいというのが本当に大きかったんです。男の子は思春期になると親と話さない、わがままな性格で自分のやりたいことをやりたい。
同年代の女の子と比べると、まだ幼さを残しているものです。

なると親と話さない、わがままな性格で自分のやりたいことをやりたい。
同年代の女の子と比べると、まだ幼さを残しているものです。
ただこの高校3年間でなにかをきっかけに、卒業するまでには「いい男だなぁ」というふうに変わるので、そういう顔つきだったり、目つきを急にするんですね。それに出会えるこの高校の教員ていうのを、僕は本当にいいなと思っています。ましてやそれが自分の好きな数学、好きな部活を通じてとなると、すごく楽しくも嬉しくもあります。
ただこの高校3年間でなにかをきっかけに、卒業するまでには「いい男だなぁ」というふうに変わるので、そういう顔つきだったり、目つきを急にするんですね。それに出会えるこの高校の教員ていうのを、僕は本当にいいなと思っています。ましてやそれが自分の好きな数学、好きな部活を通じてとなると、すごく楽しくも嬉しくもあります。
他校の生徒との違い

他の学校の生徒とうちの生徒との違いは一つだけです。
“素直”です。
これは本当に僕も驚いているのですが、部活動で学校の外に出た際、そこでいろんな方々と触れ合うわけです。特に大人の方々と触れ合う機会が多い中、「いい生徒ですね!」と言ってくださって、こちらが謙遜すると、「いやいや、本当ですよ。男子校のイメージと男子生徒
他の学校の生徒とうちの生徒との違いは一つだけです。
“素直”です。
これは本当に僕も驚いているのですが、部活動で学校の外に出た際、そこでいろんな方々と触れ合うわけです。特に大人の方々と触れ合う機会が多い中、「いい生徒ですね!」と言ってくださって、こちらが謙遜すると、「いやいや、本当ですよ。男子校のイメージと男子生徒のイメージが変わりました!」というお言葉をいただくことが多いんです。実際に他校から転任してきた教員に話を聞くと、「正則学園の生徒は素直ですよ」と返ってきます。

のイメージが変わりました!」というお言葉をいただくことが多いんです。実際に他校から転任してきた教員に話を聞くと、「正則学園の生徒は素直ですよ」と返ってきます。
わがままな一面も大人になる過程で素直に成長し、いろんなことにチャレンジする精神が身についたりと、そういう成長がこの3年間にギュッと詰まっている。OB教員である自分だからこそ、自分ができなかったことまで彼らには目一杯に楽しんでほしい。学園祭をはじめイベント一つひとつを心から楽しんで、その体験を成長の糧にしてほしいと思いますね。
わがままな一面も大人になる過程で素直に成長し、いろんなことにチャレンジする精神が身についたりと、そういう成長がこの3年間にギュッと詰まっている。OB教員である自分だからこそ、自分ができなかったことまで彼らには目一杯に楽しんでほしい。学園祭をはじめイベント一つひとつを心から楽しんで、その体験を成長の糧にしてほしいと思いますね。

男子校の魅力

男子校の魅力
この時期の男子に関しては、非常にゆっくりと成長していきますので、異性の目を気にしないで済むというのは非常にラクに生きていけるのかなと思います(笑)。
やはり思春期における異性の目はとても強力な力を持っていますので、それを気にすることで一定の基準で行動しがちになってしまいますが、男子校であれば捉われずにのびのびと生活できます。
男の子は勉強にしてもスポーツにしてもオタク気質であったり、趣味性が高いといったところもありますので、存分にとことんやっていける環境があるのかなと。そこで初めて他人と自分が違うことに気づき、また認め合って生きていくということが、自分らしさの発見に繋がっていくんじゃないかなと思います。
生徒の個性について
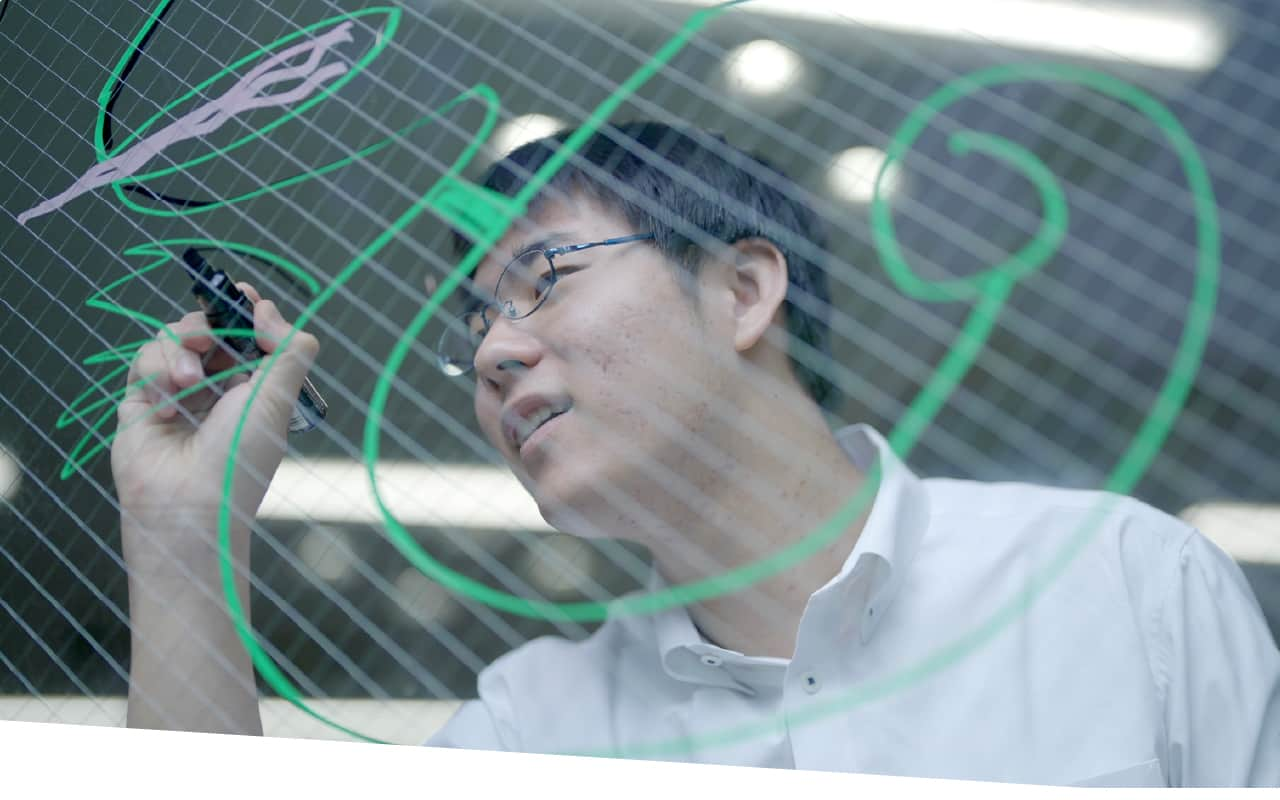
「男子校であるがゆえに、男子たるものこうあるべき」という考えを捨てること。生徒一人ひとりの特性を活かして、成長を促していければいいなと思っております。
と同時に、取り巻く環境にいる教員が生徒を一人の大人として信じてあげる、認めてあげることで、今なにをしなければいけないかを彼らが自己判断、自己決定できる状況を作ることが大切であると。

生徒に関しましては、往々にして〇〇すべきという考え方が今まで養われてきていますが、そうではなく、自分は本当は〇〇がしたいという生徒の気持ちを尊重する教員でありたいとともに、
ここ正則学園がそうした教職員が生活する場所であってほしいと思っています。
また思春期は、大人になるための準備期間。ただその中にはやはり、独立、自立、依存という気持ちが共存している時期だと思いますので、彼ら一人ひとりの個性を尊重することで、今自分には何ができるか、何をしたいのかを一緒に見つけることができると思っています。
よく親御さんたちからは、「本当にこのままでいいんですか?」と心配されるんですが、男の子に関してはそのくらいがちょうど良いんです。男の子の成長は不規則で、ある日突然ステップアップして瞬発力の強い伸び幅を見せてくれますので、待っていられる環境を作ってあげることで彼らがゆったりのびのび成長できるのだと思います。
教員としての喜び

教員に関しても生徒同様、色々なカラーを持った先生方がたくさんおられるので、そういった個性を存分に生徒にぶつけていってもらいたいというのが本質としてあります。学校というところは、なにかを教えたいという教員と、自覚的ではないにしろ何かを学びたいという生徒が出会う場だと思っています。ただその双方が一致することはあまり無いんですよね。仮にそのタイミングが3年間の間で1回でもあれば、これはものすごく堪らない
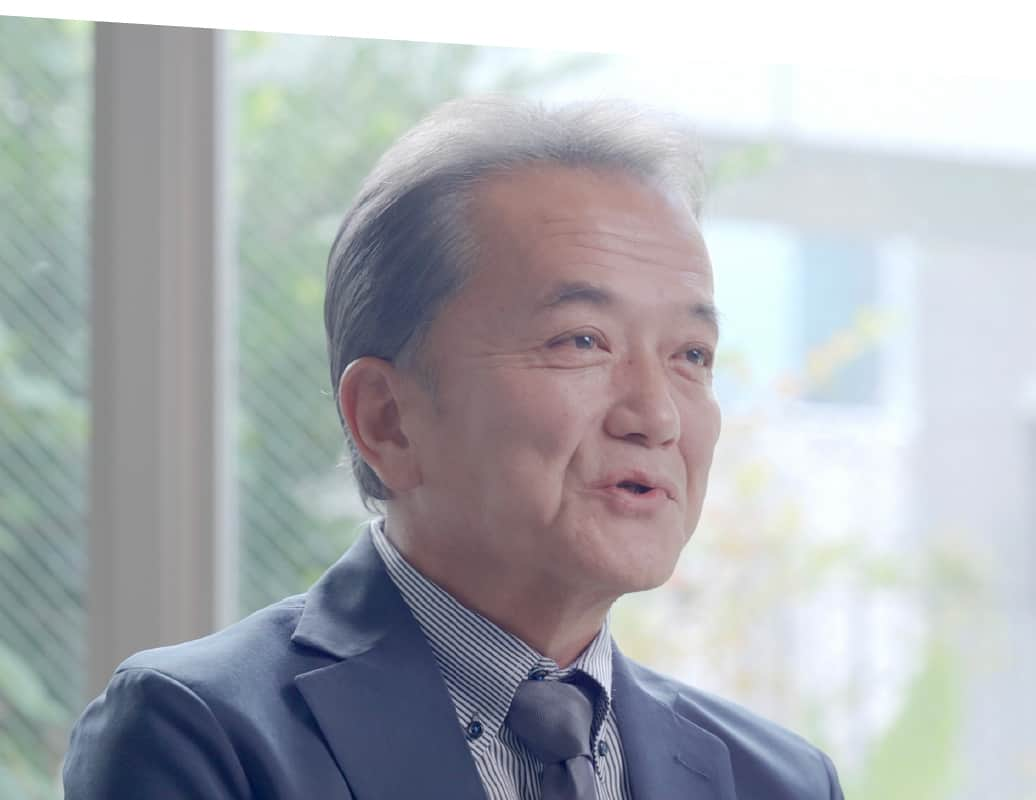
瞬間だと思います。と同時に、その回数を増やすことで生徒が成長していってくれる姿を見届けられるというのが教員としての醍醐味だろうと。
そういった部分で先生方も日々、年齢や教科を超え、研鑽を重ね、どんな授業が生徒にとって良いのかを考えながら活動してくれています。
そして、色々な種を持つ子供たちが集まって来ますので、日々どんな花が咲くのかなぁと思って水をあげたりとか肥料をあげたりしてるというのが僕らの仕事であり、その中に授業があって行事があって部活動があって、彼らの打ち込む姿を楽しみに見ていると、思いもよらない花を咲かしてくれると。こういった瞬間に出会えるのもまた、教員の醍醐味なのかなと思います。
なんらかの花を咲かせてくれるであろう生徒たちだからこそ、執拗に手入れを施したり管理し過ぎては面白くないだろうと、楽しくないだろうと思うわけです。雑草も生えたりだとか、虫が遊びに来るような大らかな花壇こそが正則学園であると。
そんな環境を作ることを日々、先生方と協力し合いながら活動している次第です。

生徒との向き合い方

生徒との向き合い方
社会人としてのルールをしっかり守らせることです。やはり社会に出ますとコミュニケーションの一番最初、挨拶や返事は大事になってきますので、そこに関しては厳しく指導いたしますし、あとは時間を守るとか、提出物をしっかり出すとか、そういった部分はやはり社会人になっても求められる部分だと思いますのでしっかり指導しています。
社会人としてのルールをしっかり守らせることです。やはり社会に出ますとコミュニケーションの一番最初、挨拶や返事は大事になってきますので、そこに関しては厳しく指導いたしますし、あとは時間を守るとか、提出物をしっかり出すとか、そういった部分はやはり社会人になっても求められる部分だと思いますのでしっかり指導しています。
あとは日々の掃除もですね。嫌なことを自分の中で折り合いをつけて、ダラダラせずに短い時間で終わらせるよう意識して指導しています。

あとは日々の掃除もですね。嫌なことを自分の中で折り合いをつけて、ダラダラせずに短い時間で終わらせるよう意識して指導しています。
その甲斐あってか、卒業後に会った生徒に「先生のおかげで今こうなれています!」という言葉をかけてもらえたりとか、実際に会って立派な社会人になった様子を見る機会が多く、嬉しく感じております。最近では4人の卒業生に会ったのですが、そのうちの2人が教員になっていたのはビックリしました(笑)。「なんで教員になったの?」と聞くと、「高校時代の思い出が良かったから」と言ってくれたので非常に嬉しかったです。
その甲斐あってか、卒業後に会った生徒に「先生のおかげで今こうなれています!」という言葉をかけてもらえたりとか、実際に会って立派な社会人になった様子を見る機会が多く、嬉しく感じております。最近では4人の卒業生に会ったのですが、そのうちの2人が教員になっていたのはビックリしました(笑)。「なんで教員になったの?」と聞くと、「高校時代の思い出が良かったから」と言ってくれたので非常に嬉しかったです。
授業で気をつけていること

私は社会科教師で、世界史やニュース検定の対策授業を担当しています。どの授業においても「百聞は一見にしかず」という言葉から、100回聞くより実際に一度その目で見てみよう!ということで、各授業で毎回動画を見せるよう工夫しています。誰かの話を聞くより自分自身で体験することが、学びにも成長においても大切だと思います。

また、〇〇しながら〇〇するということはさせず、見る、聞く、書くなど、一つひとつの行動と向き合って集中して取り組むよう指導しています。これは過去に陸上の100メートル走の選手に話を伺ったことがありまして、彼らはスタートする時に必ず呼吸を止めるそうなんです。なぜかと言うと、呼吸をしていると一歩目が出遅れてしまう。人間の身体は、〇〇をしながら〇〇をすることが上手くできないようになってるそうなんです。
そういう意味で、先生や親が「集中しなさい!」と注意するのではなく、丁寧に一つひとつの行動を取るよう促すことが生徒の自主的な成長に繋がると思います。
正則学園の生徒について

本校に来てくれる生徒の多くは、あまり褒められ慣れていないというか、保護者にも学校の先生にも同級生にもそうなんですが、なにかしら、どこかしらに多少のコンプレックスを持っている子が多いんです。なので日頃の小さな、ちょっとした良いところを見つけて褒めたりすると、笑顔で目をキラキラさせてくれるので凄く素直でいい生徒だなぁと感じますね。

例えば、私のクラスに絵が非常に得意な生徒がいるのですが、授業中もですね、教科書の端っこやノートの隅にお絵描きをしてくれるんですね(笑)。プリントの人物像に髪の毛をつけてくれたりとか、背景を描いてくれたりするのですが、それも良いことなんですけど、もっとその長所を活かせないかと生徒と話しまして、文化祭のポスターを作成してもらいました。
やはり目標ができたりだとか、そのための期日ができたりすると生徒自身もやる気が出ますし、日々ポスターの構図等を考えている時のその生徒の目がキラキラしているのが見れたのがなにより嬉しかったですね。

生徒との向き合い方

生徒との向き合い方
一番大切なのは自分で考えて動くこと。最大の目的は自立です。自立とはすなわち生き抜く力。その力を手にするため、生徒には全てを自分ごとと捉えて生活してもらいたい。例えば、なにか問題が起こった時に何故そうなったのか、その後自分がどうすれば良いのかということを生徒に問いかけるようにしています。あくまで主体は生徒。こちらから「こうすべきだ」、「ああすべきだ」と一方的に押し付けるのではなく、自分で考えてその先で行動する。こちらは問いかけだけをして、生徒たちには自分で考えてもらうことを大切にしています。

ただ最初から主体性を求めることは難しいので、私たち教員は“問う”、“聞く”に努めます。生徒たちの考えと行動に理解を示した上で、重要な部分だけはしっかりと教員として、いち社会人として指導する。そうすると生徒たちは徐々に主体性を理解し、学年が上がるごとに自分で考えて行動できるようになり、こちらがなにも指示しなくても生徒たちだけで自発的に動けるようになる。そんな成長が垣間見れた瞬間に大きな喜びを感じますね。
また少し前、卒業生と会った時に在学時代の話をしたのですが、彼がシンガポールの修学旅行の時に、私が時間を守ることを徹底して生徒たちに指導したんですね。楽しい時であれ守るべきことは守る。その教えが彼の中で非常に大きく残っていたようで、今どんな人と会う時も30分前には待ち合わせ場所に着くように行動していると言っていました。卒業してなお一層、自立した生徒の姿を見られた時はとても嬉しかったですね。
生徒の個性について

個性は十分に伸ばしていってほしいと考えます。「こうあるべき」だとか、「こうしなきゃいけない」というより、やはり一人ひとりの長所を存分に伸ばして欲しい。
とある生徒が、「自分は人と違っている」とネガティブに捉えていたことが過去にあったのですが、その生徒とじっくり話し合い、「君はそれでいいんだよ」と生徒の個性を受け止めたことで、その時期を境に自信をもって活発的に行動したり、意欲的に発言するようになったりと大きな変化が見られました。自信を持つと顔つきも大
個性は十分に伸ばしていってほしいと考えます。「こうあるべき」だとか、「こうしなきゃいけない」というより、やはり一人ひとりの長所を存分に伸ばして欲しい。
とある生徒が、「自分は人と違っている」とネガティブに捉えていたことが過去にあったのですが、その生徒とじっくり話し合い、「君はそれでいいんだよ」と生徒の個性を受け止めたことで、その時期を境に自信をもって活発的に行動したり、意欲的に発言するようになったりと大きな変化が見られました。自信を持つと顔つきも大人びて見えてきますし、発言の声量も内容も大きく変わります。自立の成長過程において自信は必要不可欠です。

人びて見えてきますし、発言の声量も内容も大きく変わります。自立の成長過程において自信は必要不可欠です。
男子校は異性の目を気にせず、あらゆることにチャレンジできる場所です。自分の弱み、カッコ悪いところまで曝け出せる。自分たちが主体的、能動的に活躍できる可能性があるのが男子校の魅力の一つ。他人との違いは個性ですから。気負わず失敗を恐れず、その結果のチャレンジがしっかり生徒たちの自信に繋がっていくように、私たち教員がサポートしていきたいですね。
男子校は異性の目を気にせず、あらゆることにチャレンジできる場所です。自分の弱み、カッコ悪いところまで曝け出せる。自分たちが主体的、能動的に活躍できる可能性があるのが男子校の魅力の一つ。他人との違いは個性ですから。気負わず失敗を恐れず、その結果のチャレンジがしっかり生徒たちの自信に繋がっていくように、私たち教員がサポートしていきたいですね。
授業で気をつけていること

生徒の視線、顔つき、様子を常に見ながら授業展開を考えています。どうしても集中力が切れる時間帯というのはありますので、生徒の状態を確認しながら少し息抜きになる雑談や、授業と繋がりのある世の中の関心ごとなど、緊張感を少し緩和させる意味合いでも話す内容は色々と変えたりしますね。
また気をつけていることでは、これは授業だけにいえる話ではないですが、基本的に教員と生徒という立場に固執することなく、教員は生徒一人ひとりの”見る角度”
生徒の視線、顔つき、様子を常に見ながら授業展開を考えています。どうしても集中力が切れる時間帯というのはありますので、生徒の状態を確認しながら少し息抜きになる雑談や、授業と繋がりのある世の中の関心ごとなど、緊張感を少し緩和させる意味合いでも話す内容は色々と変えたりしますね。
また気をつけていることでは、これは授業だけにいえる話ではないですが、基本的に教員と生徒という立場に固執することなく、教員は生徒一人ひとりの”見る角度”を変えて捉えていく必要があるなと感じています。要するに生徒との向き合い方によって、生徒はどんな方向にも柔軟に変化するということです。
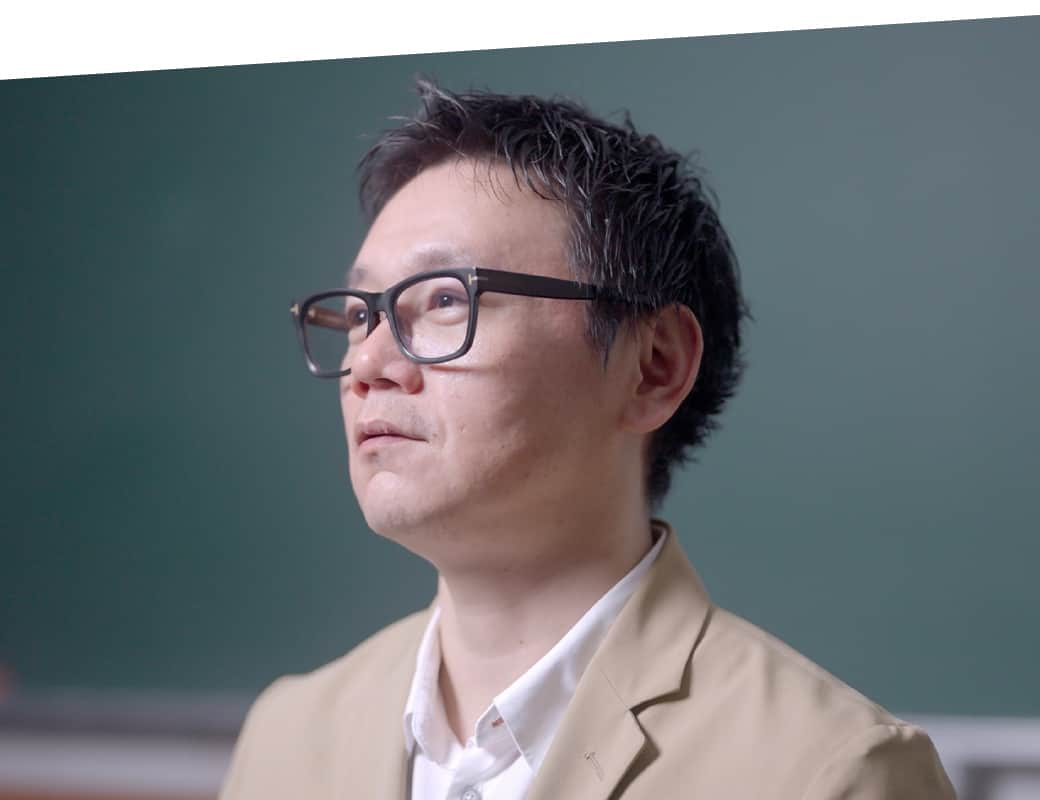
を変えて捉えていく必要があるなと感じています。要するに生徒との向き合い方によって、生徒はどんな方向にも柔軟に変化するということです。
生徒が失敗するのは当たり前。それに対して教員が感情的になったりは当然良くないこと。失敗も受け入れてこそ生徒の成長であり、また教員であっても時には失敗をするもの。しかしなかなか謝らない教員は多いんです(笑)。
生徒が失敗するのは当たり前。それに対して教員が感情的になったりは当然良くないこと。失敗も受け入れてこそ生徒の成長であり、また教員であっても時には失敗をするもの。しかしなかなか謝らない教員は多いんです(笑)。
これは教員だけではなく、大人全般に言えることかもしれませんが。「大人ってなかなか謝らなくない?」と聞くと、生徒はだいたい頷くんですね(笑)。教員であっても小さなミスはあると思います。そこでこそ、「申し訳なかった」と生徒たちに謝ることが大事なんです。謝ることによって信用も信頼も生まれますし、なにより生徒たちが謝ることの大切さをちゃんと理解してくれると思うんです。だから教員という立場からではなく、教育という観点から生徒たちを見ることがとても大事なんだと思います。